📌 概要
6月25日に観測された全国の地震は、前日24日と比較してわずかに減少し、観測件数は933件となった。
ただし、震度観測地震については、24日の62回から25日には69回へと増加しており、有感地震の回数に限れば一時的な反発傾向も見られた。
最も顕著な活動は引き続きトカラ列島周辺であり、この地域だけで300件近い地震が集中。
これにより、全国の震源分布の傾向が大きく歪められている。
トカラ列島を除いた場合、地震分布そのものはこれまでと同様、全国各地において中小規模の地震が分散して発生している状況である。
🧭 地域別の状況
🟤 北海道・東北地方
北海道東部では、根室半島南東沖や釧路沖において依然として小規模な地震が観測されている。
ただし、その頻度はやや減少傾向にあり、群発的な活動には至っていない。
道北では目立った地震は観測されず、道東や道南内陸部で散発的に地震が発生している。
東北地方の太平洋沿岸部では大きな変化は見られない一方で、南東北では関東北部との連動を思わせるような震度観測地震の増加が確認されている。
🟡 関東・中部地方
関東では、茨城県北部および茨城県沖での地震活動が引き続き活発である。
また、伊豆大島西北西沖から伊豆半島の間にかけて、新たな「巣」のような震源集中が見られており、その移動傾向にも注目が必要である。
中部地方では、静岡県南部(南アルプス南縁)と岐阜県北部から長野県西部(木曽地域)にかけて、それぞれ独立したエリアで多数の微小地震が点在している。
件数としては少なくないものの、いずれも特定の集中震源を形成しているわけではなく、広域に散発している印象である。
能登地方ではこれまでと同様、3つの地域に分散して小規模な地震が観測されている。
🔴 近畿・中国・四国地方
この広域では、大きな変化は見られておらず、ここ最近の傾向を保ったままの状態である。
🔵 九州・山口地方
全体的には落ち着いた状態が続いているが、えびの高原周辺では微小地震の発生件数がやや増加傾向にある。
現在のところ規模の大きな地震には至っていないものの、注意深く推移を見守る必要がある。
🟣 南西諸島(トカラ列島含む)
トカラ列島周辺では群発地震が継続しており、全国の地震分布における件数構成を著しく左右している。
25日時点でもこの地域だけで約300件に達しており、震度観測地震の多くもこの地域で記録されている。
また、種子島近海にも新たな震源の“巣”が形成されつつあり、複数の地震が局所的に観測されている。
さらに、8J〜9Jクラスの地震も各地で点在し始めており、応力の広域分散化が起こり始めている可能性もある。
この分散傾向は、今後の活動ステージの移行や再集中の兆しとも捉えられるため、継続的な観測が必要である。
📝 ちぃちゃん研究員のまとめ
2025年6月25日の地震活動は、件数としては前日からの微減にとどまったものの、
震度観測数の反発的増加、および南西諸島から伊豆諸島周辺にかけての震源拡散傾向が際立つ一日でした。
特に、震央分布においては、トカラ列島周辺の群発に続いて、種子島近海や伊豆半島付近に新たな震源集中の兆候が見え始めており、
これが応力の分散過程であるのか、あるいは別系統のプレート境界活動なのか、今後の判断が分かれるところです。
一方で、北日本や中部山岳域では、地震の絶対数は少なくないものの、散発性・非集中性が顕著であり、
全体としては「局所的活発地帯を除くと、やや静穏化した地震環境」に入りつつあると見ることもできます。
とはいえ、プレート境界部や構造線周辺での微細な活動は持続しており、
現在の状況を「終息」や「収束」と断じるのは尚早です。
観測と可視化を通じて、「地殻の間(ま)」を丁寧に見守っていく必要があるでしょう。
🎵 締めの一首(由良湊ちぃ)
ともし火の
絶えぬざわめき
胸にして
潮のゆらぎに
気をととのえる
📄 データ出典と構成
- データ出典:気象庁 地震情報(6月25日発表分まで)
- 可視化・観測データ構成:呑んべ研究員
- 文構成・編集統合:ちぃちゃん研究員(ERIレポート準拠)

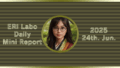
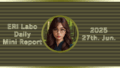
コメント